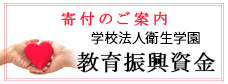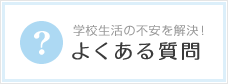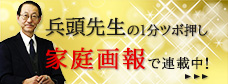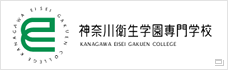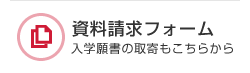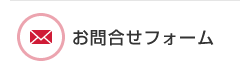東洋医療総合学科Blog
中国の針
2014年11月18日授業の様子
むかーし昔の中国の鍼灸の本には、針(ここでは道具としてのハリには、針の字を使いたいと思います)が9種類紹介されています。その中の1つを毫針(ゴウシン)と言いますが、これが今現在使用されている針の原型となっております。しかし、歴史の違いは文化の違い。中国の鍼治療と日本の鍼治療は同じではなく、毫針の形も違います。形が違うということは、刺し方が違い、その目的も違う。





写真:タオルにくるまるチナツ。キューピのタラコを思い出した(笑)

針を刺す時の基本は、芯を捉えることです。
写真:刺した直後の感想を聞いているユカ。

芯を捉えるとは、その針の長さや強度に見合った最適な力を正しく針の持ち手(鍼柄:しんぺい)から、鍼先までの方向に伝えることになります。
力が弱ければ刺さりません。
力が強ければ針は曲がってしまいます。
方向が違っても刺さりませんし、曲がってしまいます。
写真:苦戦するシホミ(笑)

日本の針は細くて柔らかい。
中国の針は太くて硬い。
まー、簡単に言うとそんな違いがあります。
写真:いざ!奥のクニミがカメラ目線。こっち見てないで刺しなさい。

日本の鍼は長時間芯を捉え続ける技術を必要とします。
中国の針は一瞬で芯を捉える技術を必要とします。
道具の性質が真逆だと、技術も真逆。そんな真逆の技術を1年生の頃から徹底的に練習していくのが東京衛生学園専門学校の実技教育。道具に振り回されることなく、道具を使いこなせるように。
写真:刺さらずふてくされるコムロちゃん(笑)

春から始まった鍼の実技授業。最近やっとお互いの足に刺せるようになってきたのも束の間、また、新しい技術を1から練習していきます。すぐに出来る事を技術とは言いません。練習して身に付けるからこそ技術と呼べるのです。厳しい練習は続くのだ!