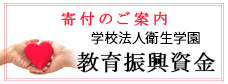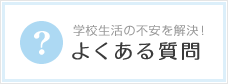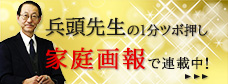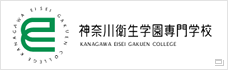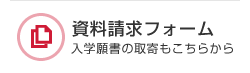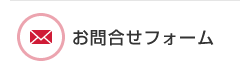トップページ 4つの学科 鍼灸あん摩マッサージ指圧 学校|東洋医療総合学科トップ 東洋医療総合学科Blog 【東洋ブログ 大希のつぶやき】3年生の鍼灸実技試験OSCE
東洋医療総合学科Blog
【東洋ブログ 大希のつぶやき】3年生の鍼灸実技試験OSCE
2025年07月26日授業の様子
いよいよ来週の29日(火)~8月1日(金)の4日間でOSCE((Objective Structured Clinical Examination:客観的臨床能力試験)が実施される。問診→身体診察(検査法、舌診・脈診・腹診)→鍼実技→灸実技→あん摩指圧の5つを、2日間、ブースを移動して試験を受けていく。問診ブースはプロの患者役や卒業生などなど学生の知らないモデル患者さんに対しておこない、2年生は問診以外のモデルになって3年生の試験内容を体験し、1年生は見学します。まさに学校を挙げての試験。卒前にこういうことをクリアしていくから、卒業して現場のスタートラインに立てるのだ。

田坂先生から鍼と灸の試験例を紹介。

せっかくなので紹介しましょう。東京衛生の卒業生にとってはごくごく「普通」の試験内容ですが。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
東京衛生学園専門学校OSCE
【鍼試験】
試験時間:4分半
課題例
〇ステンレス寸3ー2番使用
天柱 反対側の眼球へ向けて2㎝
肩井 脊柱に平行で鍼尖をやや後方へ向けて 2㎝
肩外兪 内下方45度 皮膚面から30度 2㎝
肝兪 内下方45度 皮膚面から30度 2㎝
〇ステンレス寸6ー3番
大腸兪 直刺3㎝
〇中国鍼40㎜ー0.22㎜
承筋 直刺 2㎝
承山 直刺 2㎝
試験時間:1分×2
〇銀鍼寸6ー2番
足三里 直刺3㎝
【灸試験】
制限時間 3分
課題例
透熱灸の二点交互施灸
曲池 3壮(灸点紙あり)
合谷 3壮(灸点紙あり)
足三里 3壮(灸点紙あり)
三陰交 3壮(灸点紙なし)
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
さて、マイちゃんで練習の様子を見てみよう。
まずは消毒して…

天柱(首)から刺し始めます。

拡大。

次に肩井(肩の上部)。
弾入してー。あっトントンしてー。

刺します。

そして、背中へ。

ユウカでも見てみよう。

同じように、首、肩、背中、そして腰に刺してます。
ここまでが和鍼(日本の鍼)。

腰拡大。

承筋・承山(ふくらはぎ)には中国鍼。
中国鍼は鍼管を使用しないので、トントンがない。

両手で構えて、右手の人差し指と親指で一瞬で刺します。ここまでが一連の流れ。そして…

…銀鍼を刺します。ユッキーの足三里(ひざ下)に銀鍼を刺すケイタロウ。

お灸も見てみよう。最近登場の多いフミヤで見てみよう。私に写真撮られて汗汗なフミヤ。準備中。

まずは曲池(肘)。

違う角度から。

手元アップ。

次に合谷(手)

ツボ(合谷)の上にシールが貼ってあります。「灸点紙(きゅうてんし)」と言う灸熱緩和紙です。
灸点紙について少し語ろう。昭和49(1974)年に発行された鍼灸雑誌『医道の日本』に大喜多七郎先生が『灸点紙(灸熱緩和紙)について』という投稿で、お灸の効果は素晴らしいが、この素晴らし治療がなかなか現代で普及しないことに、「効果以前の問題で、熱い・痕が残るといった,ごく自然な人間感情が拒否反応を示しているのではないか」と述べ、灸療普及のための試案として15 mm の難焼性の台紙に、金属の薄膜を接合させ、その中央に針先ほどの孔を開けた『灸点紙』を試作し発表しました。その後、この灸点紙は新しい形のお灸、痕がつかないお灸、顔にもすえられるお灸として商品化されました。東京衛生学園では、人体へのお灸はこの「灸点紙」を使用するところから始めて、直接施灸をするところまで技術を上げていきます。灸点紙、素晴らしい道具です。

足三里(膝下)。ここまでは灸点紙を使いますが、最後の三陰交(内くるぶしの上)は直接やりますが、てきぱきお灸しないと、時間内に三陰交までいきませーん。

はい、ってか感じで3年生は練習を頑張っております。
授業でも紹介しますが、ボクシング漫画『はじめの一歩』の鴨川源二会長の名言「努力した者が全て報われるとは限らない。しかし、成功した者は皆すべからく努力している」という言葉が好きです。学生中の練習が嫌々でもいいんです。やらされたっていいんです。なんであれ努力したことには変わりないのです。そして、学生中の努力が、卒後の成功に影響する、そんな学校教育を常に追究していきたいと高橋は思っております。