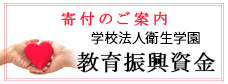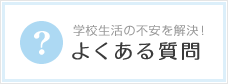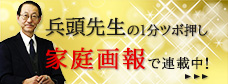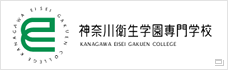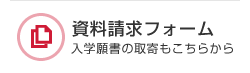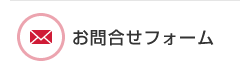トップページ 4つの学科 鍼灸あん摩マッサージ指圧 学校|東洋医療総合学科トップ 東洋医療総合学科Blog 【東洋ブログ 大希のつぶやき】中医鍼灸 吸玉療法
東洋医療総合学科Blog
【東洋ブログ 大希のつぶやき】中医鍼灸 吸玉療法
2025年10月14日授業の様子
中医学といえば東京衛生学園、東京衛生学園といえば中医学。
そんな東京衛生学園の中医学教育を長年に渡って支え、そして発展し続けてくださっているのが講師の河原保裕(かわはら やすひろ)先生です。河原保裕先生は本校の卒業生であり、中国一と言っても過言ではない鍼灸の臨床をしている天津中医学院(現天津中医薬大学)への研修留学を経験され、現在は埼玉県の大宮で治療院を開業しております。長年、鍼灸師会の会長も務められた、多忙な先生ですが、後輩たちの為に指導に来てくださいます。うちの教員は全員先生の教え子、私にとっても恩師であります。
写真:吸玉のサイズを説明をしている河原保裕先生

ちょっとだけ私高橋の昔話をすると、熱海にある鍼灸専門学校を卒業して東京衛生学園の臨床教育専攻科(教員養成課程、2019年3月の卒業生で終了)に入学して、中医学に出会います。中医学を全く知らない学んでこなかった私は、放課後に特別講義を受けていたのですが、正直全く理解できませんでした。兵頭明先生のツボの授業もあったのですが、中医学の基礎理論を知らない私にとってはツボの説明も理解できない、そんな状態でした。臨床教育専攻科の臨床実習は、学生とはいえ鍼灸師の免許を持っていますので、卒前とは違って一人で治療するのが当たり前でした。いろいろな治療方法の先生方が指導して下さります。そんな中で、自分の治療法(中医学)を押し付けず、私の治療法を尊重し、でも私が見立てを説明することで、自分だったらと中医学的な考え方やアドバイスをして下さったのが河原保裕先生でした。私が中医学を学ぼうと思ったきっかけです。中医学に興味を持ったというより、河原保裕先生に興味を持ったという感じです。
写真:吸玉のデモをしている河原保裕先生

さて、「吸玉(すいだま)」ですがご存じでしょうか。一般的には「カッピング」といったほうが知っている人が多いでしょう。オリンピックの水泳選手の体についている「跡」を見たことがあると思います。専門的には「角」の文字や「罐(缶)」の文字も使用され、「吸角(きゅうかく)」「抜罐(ばっかん)とも言われます。古代は獣の「角」を使っていたから、また「罐(缶)」は「容器」の意味でも使用され、「竹罐」「陶罐」「銅罐」「鉄罐」「ガラス罐」などの言い方もあるようです。「吸玉」の中に火を入れるとこと、内部が陰圧になりますので、そのタイミングで目的の場所に置くと皮膚に吸い付きます。

上の写真の先生の手元をアップしてみると…。

先生の手が、そっと「吸玉」を持っているのが分かりますよね。ついつい、押し付けてしまうのですが、あくまで「陰圧」を利用して「吸い付き」ますので、写真のような「そっと」な手つきが重要になります。写真は「吸玉」が3つ付いていますが、先生は微妙な「火加減」で「陰圧」をコントロールして吸い付く力を調整しているのを解説しています。この後、皆で先生の付けた吸玉を触ってその違いを確認しました。吸玉の治療効果は「以疏散爲主」と表現されます。人体の浅い気・筋・肉に対して滞っている気や血を散らすことを目的とします。
写真:ベッドをまわって個別に指導を繰り返してくださいます。

ちょっとしたコツの部分を個別に見極め指導していきます。

あとは数をこなすのすのみ!

ってことで、中医鍼灸の多くの授業の中から本日は「吸玉」療法を紹介させていただきました。中医学の考えに基づき行う「吸玉」。カッピングと見た目は同じでも、その目的や理論には中医学が背景にあるのが、東京衛生学園スタイルです。中学を学ぶなら東京衛生学園、東京衛生学園といえば中医学なのです。