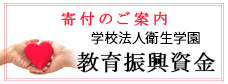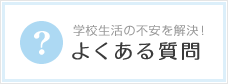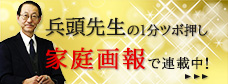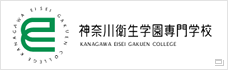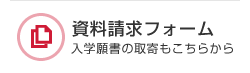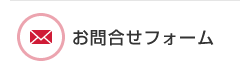トップページ 4つの学科 鍼灸あん摩マッサージ指圧 学校|東洋医療総合学科トップ 東洋医療総合学科Blog 【東洋ブログ 大希のつぶやき】大鍼からのー長圓利挫刺
東洋医療総合学科Blog
【東洋ブログ 大希のつぶやき】大鍼からのー長圓利挫刺
2025年08月02日授業の様子
本校の卒業生で「東京九鍼研究会」会長の間純一郎先生が授業のお手伝いに来て下さってます。これまで、「刺絡(しらく)」と「火鍼(かしん)」の授業の様子をブログで紹介させていただきました。
【東洋ブログ 大希のつぶやき】中国鍼灸 火鍼

【東洋ブログ 大希のつぶやき】血を出す三稜鍼
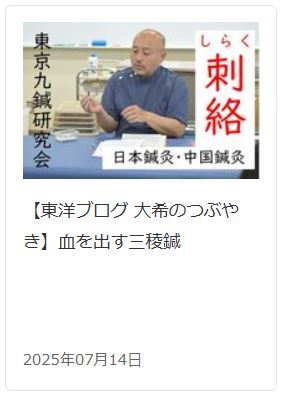
最後の授業は、刺激多めの「大鍼」「長鍼」「圓利鍼」「坐刺鍼」でした。
写真:大鍼の解説をする間先生。手元を拡大すると…


鍼が太いのが分かりますかね。
写真:上が大鍼。下が毫鍼なので、通常の鍼です。ぱっと見では大鍼が太いかは分からなくても、毫鍼(通常の鍼)が細いのは分かりますよね。でも、先ほどから言っているように、毫鍼が、その太さが通常なんですよ(笑)

大鍼の練習法を紹介している間先生。竹串をティッシュペーパーの「箱」に刺す練習。

練習開始!

練習!

練習練習。

練習練習練習!

それでは人体に。

人体には、最初「鍼管」を使用して刺してみます。

ユ、ユッキー…。

タクミが腰に大鍼を…

はい、いい感じー。太い!

続いて「長鍼」。

コダさんの手元をアップ。「長鍼」っていうだけあって、長いのが分かりますよね。

次は「圓利鍼(えんりしん)」。これまた特殊な鍼です。

刺し終わったところ。

「圓利鍼(えんりしん)」は、その形状が特殊で、人の身体に刺さっていく部分(鍼体)が鍼の先に向かって徐々に細くなっていきます。通常の毫鍼は、鍼の先(尖)だけが鋭くなっています。また、鍼柄の上鍼に玉が付いており、ここを持って、まるで車のシフトレバーを操作するかのように縦横無尽に鍼の先端を移動させ、頑固な筋肉のコリなどを砕きます。強い痛みに有効です。

そして、最後は挫刺鍼(ざししん)。刺せる鍼灸師も少ないと思うが、そもそも知らない鍼灸師がほとんどだろう。間先生の手元をアップすると…


挫刺を知らない方の為にちょこっと説明すると、昭和 29 年に長野県の塩沢幸吉先生が考案した鍼法です。塩沢先生は「挫刺に適する特殊な鍼を使用して、表皮・真皮および皮下組織の一部を極めてミクロな状況下において刺切し、挫滅することによって、固有の刺激を発現せしめ、生体の機能変調を調整し、もって個体を正常に導くことを目的とする
療法である」と定義しています。簡単に言うと、挫刺鍼という特殊な鍼で皮膚に開けた穴から、皮膚の下の組織を輪にして引っかけて削り取る、といった感じでしょうか。私も間先生の師匠の石原克己先生から教えていただきましたが、習得するのが難しい鍼の一つでした。超痛いし(笑)
写真:最後の授業で記念撮影。

鍼灸を学ぶと、思想、理論、技術と本当に奥が深い。これら3つを自分の中で落とし込んでいく作業が永遠に続いていくのが鍼灸沼です(笑)。
間先生ありがとうございました!