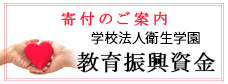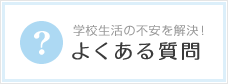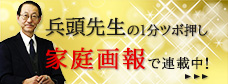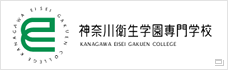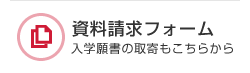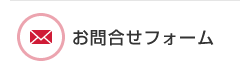トップページ 4つの学科 鍼灸あん摩マッサージ指圧 学校|東洋医療総合学科トップ 東洋医療総合学科Blog 【東洋ブログ 大希のつぶやき】打鍼 後編
東洋医療総合学科Blog
【東洋ブログ 大希のつぶやき】打鍼 後編
2025年09月01日授業の様子
打鍼の専門家である関信之先生に3年生の授業を手伝っていただいております。
前回の授業の様子をこちらのブログで紹介しました→【東洋ブログ 大希のつぶやき】打鍼 前編
今回は、前回の授業の続きの紹介となります。
打鍼においては、まずは「腹診」が重要となりますので、まずは前回の授業の復習です。お腹の「硬いところ」と、「柔らかいところ」を見つけていきます。

関先生の見立てを経て、触ってみます。こういった、手から手への実技指導というのがいかに重要か。

そして、硬いところに、まずは「刺さない打鍼」をしていきます。ここまでが前回の内容でした。

「腹診」における触診は、通常仰向けの状態で行います。しかし、腹診で得られる情報には、視覚的なものがあり、これがまた重要となってきます。そこで、お腹の色、そして何より形の見ていきます。鍼をする前と後では、立った状態で見たほうが確認しやすいのと、打鍼を受けた側も立った状態のほうが身体のバランスの違いが感じやすいです。

関先生にチェックしてもらいながら、自分の見立てと照らし合わせていきます。

ってことで、やってみやってみましょう!

お腹の硬いところに「刺さない打鍼」。そして、今回はお腹の柔らかいところに「刺す打鍼」です。

手元をアップするとこんな感じ。細くて長い鍼が人差し指と中指の間にあるのがわかりますかね。細いといっても、普段刺している「毫鍼」に比べるとめちゃめちゃ太いです。ちなみに、爪楊枝より気持ち細いくらいです。

みなさん、なかなか苦戦しておりますが、なんとかやっております。

お互いにやっては、お腹を確認。奥のベッドではお腹の確認しているね。

打鍼後にも、こんな感じでお腹の確認。

そうそう、打鍼を知らない方の為に少し説明を加えると、長くて太い鍼を小槌で打つ「打鍼」すが、実際にお腹に刺のほんの数ミリです。小槌で叩くってことは、勢いよく深く刺すように思ってる人もいるかも。では、なぜ「小槌」で叩くのか。それは、叩いた時の「振動」こそが治療効果に関係しているからです。このへんって、やはり日本の伝統鍼灸の特徴の一つだったりしますねー。いやー、「打鍼」は奥深いよ。